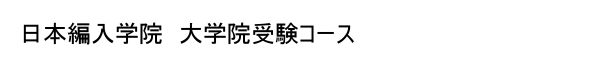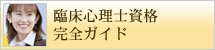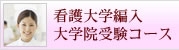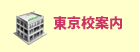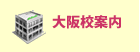毎年、計3回の試験(平成23年度は10月、11月、2月)が実施され、小論文と口述試験が同日に果たされる。平成22年度までは、小論文には、日本語の読解と記述および英文の読解の二つの内容が含まれ、文章読解力や記述力とともに英語力の試験が果たされてきた。しかし、平成23年度からは小論文に含まれる英語はなくなる予定である。これにより従来小論文のなかに果たされてきた日本語の読解や記述の部分が拡大するわけだが、その形式や内容はこれまでと大幅には変わらないと予想される。
これまでの小論文の形式は日本語については、A4で1ページ半から2ページ程度(2500字から3900字程度)の文章を読ませ、文章の読解に関する問題を答えさせた後、文章に関わるテーマにつき、400字程度の文章を書かせるといった形式が主流であった。時間内(平成23年度は90分)に答案を完成させるには決められた時間の中で、文章を正確に把握し、手際よく文章をまとめる訓練をつむ必要がある。
なお、小論文のなかに英語が含まれていた年度においては、上記の日本語の問題に、A4で半ページから1ページ程度の英文についての問題が他に加えられ、英語が廃止された場合、日本語の文章の分量は上記よりやや多くなると予想される。
内容は大学の現状、組織人の特徴、市場調査、概念や事実、イノベーションといった広い意味で、経営学に関わる問題に関するものが多い。ただし、専門性が強い文章というより、エッセイに近いもので、入学してからの学習能力を幅広く試そうという意味合いが強い。経営学をとりあつかった新書を何冊か読み、経営学の学習内容を基本的なことでいいから触れておくことが対策になると思われる。また、実際の例えば日本の企業の経営を扱った文章も新書や新聞等で触れ、その内容を触れるとともに、自分なりの経営に関する考え方を研ぎ澄ませておくことも重要と思われる。それにより、文章に付随したやや長文(400次程度)の問題にも手際よく対処できるようになるし、また、口述試験においても試験官に経営学の学習能力や意欲をアピールできるようになるであろう。英語が廃止されたので、試験対策といった視野の狭い勉強を重ねるより、新書や新聞といった経営学に関する文章を通じて、改めて自分が大学院に入ってどうして経営学を勉強するのか、大学院で学んだ経営学を今後の人生でどう生かすかといった自分への問いかけをすることが、幅広い意味で、入学試験(小論文と口述試験)の最も効果的な対策になるかもしれない。
例年、問題Ⅰと問題Ⅱの大問2問構成である。それぞれ50点、50点の配点である。問題ⅠはA4で1ページから3ページぐらいの英文を読ませ、それについて、その内容およびそれに関連した内容を問う形式の問題である。問題Ⅱは日本文を読ませて、その内容およびそれに関連した内容を問う形式の問題か、あらかじめ短文で誘導的に用意されたテーマに関して1200字程度の小論文にまとめさせる問題のどちらかである。問題Ⅰや問題Ⅱの問題のなかにも短文で内容の把握力を問う問題とともに、500字で受験生の考えを尋ねる問題も含まれ、全体として「小論文」の科目であると考えてよい。
問題文の内容はサブプライム、マーケットシェア、経営戦略など経済学や経営学のホットな問題を取り扱った問題が多い。とりわけ、経営戦略を扱った問題文が出題される際には、コンティンジェンシー理論やコスト優位といった、経営組織論や経営戦略論の基本的な概念や考え方についての素養を問う問題も含まれるため、経営学の基本的な事項については、まとめておき、なおかつすぐに記述・説明できる力をつけておくことが望ましい。また、500字程度の長目の記述問題では、経営組織論や経営戦略論の基本的な概念や考え方についての説明のみならず、実際の経営問題に照らし合わせてどうか、とか受験生の考え方自体を聞く問題もあるので、経営組織論や経営戦略論の基本的な概念や考え方のマスターと併せて、実際の経営問題を取り扱った新書を併読し、自分の問題意識を整理しておくことが望ましい。また、経済の問題を取り扱った問題の場合には、経営学ほどには経済学の学習事項に踏み込んで問われることはないが、
~年の不況について知ることを記せ、~の時代はどのような時代であるか、記せ、といった大型の記述問題や不況に対する経済政策を企業戦略と併せて500字で問う問題等も含まれているため、あらかじめ経済学の基本的な学習事項および現代の経済の特徴について新聞や新書を通じてまとめておくことが望ましい。
一方、短文誘導型の小論文の場合には、インターネット、情報開示といった現代の事象がどのように実際の経営に影響を与えるかを尋ねたり、消費者の特徴だった動向について実際の経営者であったらどう対処すべきかを尋ねたりする、実践的な経営センスを問う問題が多い。なぜ、専門職課程で経営学を学ぶかといった根本的問題を自分に問いかけながら実際の経営問題に思考をめぐらすといった基本的な態度が案外効果的な対策なのかもしれない。
小論文・経済学、小論文・経営学、小論文・都市・地域政策、数学の4つの出題分野が用意されている。その中から1つの出題分野を選択して解答することになる。小論文・経済学は大問2問が用意され、世界金融恐慌や少子化といった、現実の主にマクロ経済で問題になっている事象について問われていることに関して論述によってまとめさせる問題、あるいは、レモンの市場や内生的成長論といった、ミクロ経済学やマクロ経済学の理論で登場する事項に関する問題などが出題される。前者の現実の経済に関する論述についてはただ、現実の経済現象をなぞればよいというものではなく、議論をする際に背景として必要となるミクロ経済学やマクロ経済学の基本的な理解が必要となる。また後者のミクロ経済学やマクロ経済学については、資格試験等のテキストに見られる、ミクロ経済学やマクロ経済学の簡単な計算がこなせればそれでよいというものではなく、論述形式による解答も含まれるため、各事項のしっかりとしたそれらの理解が必要となる。問題レベルとしては大学院入学試験のなかでもやや難といえる。小論文・経営学は大問2問が用意され、コンビニエンスストアやスーパーマーケットでの販売、長期経営計画、キャリア・プラン、租税が及ぼす影響といった現実の経営上の問題に関して、経営学の観点から分析・記述することが要求されている。組織論や戦略論の理解に関する問題がストレートでなく、その事項の中で何を使うか一見するとわからない隠された状態で出題されており、これもレベルはやや難といえる。小論文・都市・地域政策は大問2問が用意される。1問は都市・地域政策に関する、4つぐらいの基本的な用語を説明・論述する問題、もう1問は、都市・地域政策で問題となっている事項について適切な論述を加える問題である。都市・地域政策を学部時代に専攻した者にとっては、他の科目にくらべ比較的容易な出題といえる。小論文・経済学や小論文・経営学、小論文・都市・地域政策の対策として、経済学(ミクロ経済学、マクロ経済学)や経営学、都市・地域政策の基本的な事項を代表的なテキストを利用してマスターするとともに、現実の経済や経営、都市・地域政策で問題となっている事象について、TV、新聞、新書等で丁寧にたどっておくことが必要になろう。また、論述が主であるため、過去問等を記述したものを第三者に読んでもらい、適宜評価をしてもらうということも必要になろう。
数学については、6問から9問程度の問題が与えられ、その中から3問選択して解答する形式である。内容は行列、法線、二重積分、テイラー展開、区間推定、確率、線形空間、回帰分析といった、大学教養課程レベルの基本的な事項に関する問題である。ただ、数学といっても、確率・統計からの出題が含まれていることに注意されたい。また、レベル的にも純粋な数学については大学院入試の標準的なレベルより上と考えられるが、確率・統計についてはそれに比べ平易な出題である。純粋な数学についても確率・統計についても代表的なテキストで多くの問題をこなすとともに、解答プロセスの記述も要求されているため、過去問を解答することによって得られた答案を第三者に見せることも必要となろう。
大学院受験をご希望の方は下記リンクよりご連絡ください。
無料カウンセリング(受験相談)を行っております。
お問い合わせは、日本編入学院
東京校 TEL.03-5464-8815 E-Mail:honkou@hennyu-japan.com
大阪校 TEL.06-6195-6731 E-Mail:osaka@hennyu-japan.com
通信 TEL.03-5464-8817 E-Mail:tusin@hennyu-japan.com